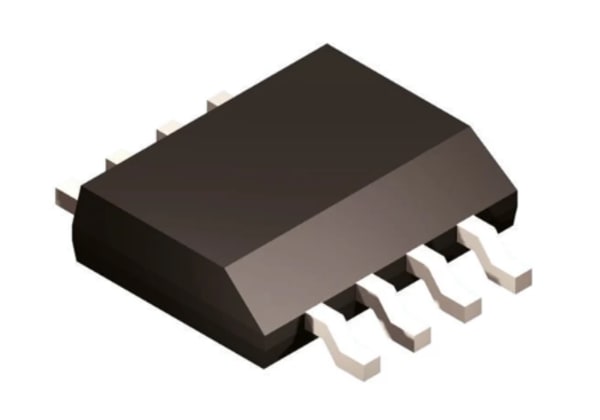- 発行日 2024年4月26日
- 最終変更日 2025年1月8日
- 1 分
JFET(接合型電界効果トランジスタ)とは?特徴や回路構成についてわかりやすく解説!
JFETは接合型電界効果トランジスタの略称で、トランジスタの一種です。増幅回路やスイッチング素子として用いられます。今回の記事ではJFETの概要と特徴、原理や用途についてわかりやすく解説します。

JFET(接合型電界効果トランジスタ)とは?
JFETはJunction Field Effect Transistorの略で、日本語では接合型電界効果トランジスタと呼ばれています。JFETは電界効果トランジスタの接合型版であるため、まずは、電界効果トランジスタの概要を解説します。
電界効果トランジスタとは、流れる電流を電圧で制御するトランジスタのことをいいます。通常のトランジスタと比較して、消費電力が低く、高周波での動作に適しているという特徴があります。
電界効果トランジスタの構造は大きく2つに分けることができます。それがMOS FETとJFETです。
MOSFETは金属で絶縁体を挟み込むような構造をしているのに対して、JFETは半導体を繋ぎ合わせた構造を持ちます。
JFETは「接合型」と名称がついていることからわかる通り、半導体を接合することによって作られたFETです。
JFETもトランジスタの一種であるため機能は基本的なトランジスタと同じですが、動作速度やスイッチングの性能はトランジスタよりもFETが優れているという特徴があります。
JFETの特徴
この章ではJFETの特徴について解説します。
電流を電圧で制御する
FET以外のトランジスタは電流で電流を制御しますが、JFETは電流を電圧で制御する特徴があります。
具体的にはソース-ドレイン間に流れる電流を、ゲートに電圧を印加することで制御します。電圧を使用して制御することで、電圧を生成する一般的な回路を利用できるため、回路全体の設計も容易になるメリットがあります。
高入力インピーダンス
JFETはバイポーラトランジスタと比較して、入力インピーダンスが高い特徴を持ちます。
入力インピーダンスが高いことで以下のようなメリットがあります。
- 外部から受け取る信号の損失を最小限に抑えられる
- 接続されている他の回路への負荷が少ない
入力インピーダンスが高いことは回路設計において重要です。電子回路においてはある回路が他の回路に影響を及ぼす可能性を考えなければなりません。そのため、FETのような他の回路に影響を及ぼしにくい素子を使うことは、設計を容易にするというメリットを生みます。
高速なスイッチング
高速なスイッチングを実現するためにはゲートに印加される電圧に俊敏に反応して、チャネル幅を変化させる必要があります。
JFETは単純な構造であり、電圧が変化した時の充放電を短時間で行うことができるため、高速なスイッチングが可能となっています。
PN接合を用いた構造
バイポーラトランジスタはP型もしくはN型の半導体をもう一方の半導体で挟み込んだ構造をしていますが、JFETはP型もしくはN型の半導体の土台にもう一方の半導体をセットした構造をしています。
単純な構造であるため低コストで製造できるメリットがあります。一方で、バイポーラトランジスタに比べて、ノイズに弱いというデメリットがあります。
JFETの原理と仕組み
この章ではJFETの動作原理と仕組みについて解説します。
3端子で構成される
JFETはバイポーラトランジスタと同様に、3つの端子を持ちます。3つの端子の名称は以下の通りです。
- ソース(Source)
- ゲート(Gate)
- ドレイン(Drain)
ソース-ドレイン間に流れる電流を、ゲートに印加する電圧によって制御します。JFETではゲートに電圧を印加しない状態ではソース-ドレイン間に電流が流れ(オン状態)、ゲートに電圧を印加することでオフ状態となり、電流が流れないようになります。
JFETはその構造によってNチャネル型とPチャネル型に分かれます。機能が変わりますので、それぞれ解説します。
Nチャネル型JFET
Nチャネル型のJFETはN型半導体を土台にして、P型半導体をその上に接合した構造となっています。N型半導体の両端がソースとドレインであり、P型半導体がゲートの役割を果たします。
ゲートに電圧を印加しない状態ではソース-ドレイン間に何も遮るものがないため、電流は流れ続けます。
一方でゲートにマイナス電圧を印加すると、PN接合されている接合部の空乏層が拡大され、電子の流れが遮断されるため、電流は流れなくなります。(オン状態)
電流が流れなくなった状態をピンチオフ、このときの電圧をピンチオフ電圧といいます。
Pチャネル型JFET
Pチャネル型のJFETはNチャネル型のJFETとは逆の構造をしています。
P型半導体を土台にして、N型半導体をその上に接合した構造で、P型半導体の両端がソースとドレインであり、N型半導体がゲートの役割を果たします。
Nチャネル型JFETと同様で、ゲートに電圧を印加しない状態では、ソース-ドレイン間に電流は流れ続けます。
ゲートにプラス電圧を印加すると、空乏層が大きくなり、電流が遮断されます。
Nチャネル型JFETとPチャネル型JFETでは、印加する電圧がマイナスとプラスで異なることに注意しましょう。
JFETの用途
JFETはトランジスタであるため、一般的なトランジスタ同様に増幅やスイッチングに用いることができます。
特にJFETは高速スイッチングが得意な素子であるため、スイッチングに多く用いられます。
ただし、ノイズに弱い特徴があるため、ノイズの影響を考慮しなければいけない回路では、JFETはあまり用いられないようです。
まとめ
この記事ではJFET(接合型電界効果トランジスタ)について解説してきました。
JFETはPN接合を用いたトランジスタで、電流を電圧で制御する点が特徴です。高速なスイッチングを有しているため、スイッチング素子として利用されることが多いです。
現在ではMOSFETが主流となっていますが、JFETが使われることもあります。