- 発行日 2023年10月11日
- 最終変更日 2023年11月9日
- 5 分
VCO(電圧制御型発振器)とは?役割や仕組み、種類について徹底解説!
VCOは、電圧制御型発振器の略称です。私たちの身の回りにはVCOの技術が活用された製品が数多くありますが、この役割や仕組みについて詳しく知る人は少ないかもしれません。この記事では、VCOの役割や進化の流れ、種類などについて解説します。

VCO(電圧制御型発振器)とは?
VCOとは、電圧制御型発振器のことを指します。出力される周波数と入力電圧が比例する電子発振回路を総称したものです。
基本的に発振器は、周期的なAC信号を生成しますが、VCOにおいては、入力された電圧によって周波数が決定します。この仕組みを応用して、あらゆる電子機器のコントロールを行い、正常な稼働をアシストします。
ここでは、以下の3つに分けてVCOの技術について解説しますので、詳しく見ていきましょう。
- VCO発振器の種類
- VCOが担う役割
- 発振器回路における進化の流れ
1.VCO発振器の種類
VCO(電圧制御発振器)は、生成する波形ごとに以下の2種類に分類することが可能です。
- 高調波発振器:正弦波の波形を生成する
- 弛張発振器:三角波形もしくはのこぎり波形を生成する
目的や用途ごとに適したVCOには違いがあり、代表的な用途の例を挙げると以下の通りです。
- ファンクションジェネレータ:あらゆる電気波形を電圧信号として出力できる
- フェーズロックループ:ノイズを抑えて入力信号と出力信号を一致させる
- トーンジェネレータ:人工的に電気信号を音に変換する
- クロック発生器:信号を特定の周期で制御、変換する
- 周波数シンセサイザ:高調波合成を使った無線通信器の発振回路。携帯電話やTVチューナーなどに使われている
電気信号を変換することが主な目的として使われているため、家電や通信機器を始めとした製品になくてはならない存在だといえます。
また、VCOを選ぶには、以下のポイントを確認して選ぶことが重要です。
- 周波数範囲 :最小・最大発振周波数
- 出力電力:VCOで生成可能な出力電力
- チューニング電圧:発振周波数を調整し、目的ごとに最適化できる電圧レベル
- チューニング感度:電圧を印加した状態においての発振周波数の変動レベル
- 供給電圧:動作修正に求められるDC電圧
- プル:負荷変動に応じた出力周波数のドリフト
- プッシュ:電源電圧の変動に応じた出力周波数のドリフト
- 位相ノイズ:出力信号の明瞭度
2.VCOが担う役割
多くの電子機器やアプリケーションにおいて、周波数の振れ幅をコントロールすることによって正常に動作させています。VCOには、発振周波数の範囲を決定・制御する役割が求められ、VCOが正しく制御されていなければ、安定的に電子機器を動作させることは不可能です。
VCOは入力する電圧によって周波数を制御できることから、電波を使うほとんどの電子機器では、フィードバック回路と複合的に使用して、安定した周波数の確保を目的として使われています。
たとえば、日本では関東と関西で供給される電気の周波数には違いがあります。VCOが電圧を感知していずれの周波数でも使用できるように調整される「ヘルツフリー」の製品も存在するのです。
しかし、モーターやトランス、電子タイマーなどはそれぞれの周波数を基準としているものもあるため「西日本60Hz、東日本50Hz」の表記を確認する必要があります。
周波数を誤って使用してしまうと、性能基準に満たないだけではなく、故障してしまう原因となるおそれがあります。そのため、家電製品については適切な周波数を確認したうえで購入することが重要です。
3.発振器回路における進化の流れ
VCOは1910年代に開発されて以降、凄まじいスピードで進化を続けています。VCOは当初、真空管を構成することによって発振できることを応用した電子発振器が発明されました。これは非常に大型だったため、一般的な製品に活用することは難しかったようです。
進化の流れを具体的なデバイス名にすると、以下のように表せます。それぞれの特徴も併せて解説します。
- 真空管発振器:高周波誘導加熱装置として現在でもよく使われている
- トランジスタ発振器:外部帰還型発振回路としてスピーカーなどに使われている
- 発振器モジュール:正弦波を出力し、安定した信号を生成できる
- RFIC発振器:1つのチップに多くの機能を搭載可能。通信機器に使われている
VCO技術の発展とともに、軍事用の通信機器に使われるようになり、小型化が進められるとともにラジオやテレビなど、一般的な製品にも応用されるようになりました。
さらなる小型化が進められていき、VCOモジュールが一般的な市場で立場を確保するのは、携帯電話が普及するまで待たなければなりません。
1990年代に携帯電話が爆発的な普及を見せるなか、超小型モジュールの需要が高まりました。改良を重ねることにより、低コスト(1USD)かつ超小型(4×5×2mm)のものを日本で量産することに成功しました。
そして、現在では電波を使用して通信する機器において欠かせない存在として多くの製品に組み込まれています。一例を挙げると、無線や通信、コンピューターなどに関連する製品のほとんどに使われており、ほかにも周波数や位相変調の用途が求められる機械に採用されています。
VCOの仕組み
VCOには、大きく分けて以下の3つの形態があります。
- ディスクリート:任意の周波数範囲と同調範囲をカスタマイズできる
- モジュール:小型かつ費用対効果が高い
- モノリシック:超小型かつRFトランシーバ機能と同じプロセスで実装可能
いずれのVCOも発振回路を構成するコンデンサにバリキャップダイオードを組み込み、電圧ごとに発振周波数を変化させる仕組みが採用されています。
つまり、バリキャップダイオードに与える電圧を高めると発振周波数は上がり、電圧を低くすると発振周波数は下がります。この現象を応用して電子機器の動作をコントロールしています。
また、発振周波数が起こる流れとしては、まずVCOに電源を加えることによって発振が起こり、コイルの値と並列されているバリキャップダイオードの合計値によって決定されるのです。
さらに、発振トランジスタが有する電極間容量も加算されます。これらに加えて、構成する回路によって変調・増幅することも可能です。
こちらの例を挙げると、以下の2つが主に実用化されています。
- FM変調
- 緩衝増幅
変調用のバリキャップダイオードを構成に組み込むことによって、周波数の制御と変調の両方に対応できるようになります。
また、バッファアンプを組み込むことによって外部からの影響を最小限に留めることも可能です。
VCOの種類は3つ
VCOの種類には、以下の3つが挙げられます。
- Ring-VCO
- LC-VCO
- VCXO
ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
1.RING-VCO
Ring-VCOは、インバータを奇数段、リング状につなげた発振回路のことを指します。特徴としては、インバータの段数とゲートにギャップが生まれることを応用して発振周波数を制御します。
また、出力される周波数の範囲は幅広く、一般的に採用されているVCOの種類のひとつです。しかし、後述するLC-VCOやVCXOと比べると、周波数の安定度に劣る傾向があります。
これは、電流によって周波数を制御しますが、電源ノイズによる影響を受けることが理由です。
しかし、低雑音クロックジェネレータを組み込むことにより、電源ノイズの影響を抑える・雑音の抑制を期待できます。
2.LC-VCO
LC-VCOは、コイルとコンデンサをつなぐことによって、発振させる回路のことを指します。コンデンサに、可変容量ダイオードを組み込むことによって、VCOとして使用することが可能です。
LC-VCOは、Ring-VCOよりも位相雑音特性が低い傾向にあるため、位相雑音に影響を受けやすい製品やアプリケーションに使用されています。
また、高周波数出力にも対応しているため、高周波数が求められるPLLにも取り付けられることが一般的です。
3.VCXO
VCXOは、LC-VCOのコイルを水晶振動子へと組み替えた構成のものを指します。
ほかのVCOと比べると、周波数安定度が高いことが特徴です。たとえば、REFクロックが遮断されてしまったとしても、ほぼ一定の出力を維持することができます。
その一方、出力周波数範囲が狭いことや回路規模が大きくなってしまうことがデメリットです。
こちらのVCOは、ジッター減衰器などに取り入れられ、不要なノイズを除去することを目的として活用されています。
VCOにおける仕様の決定方法
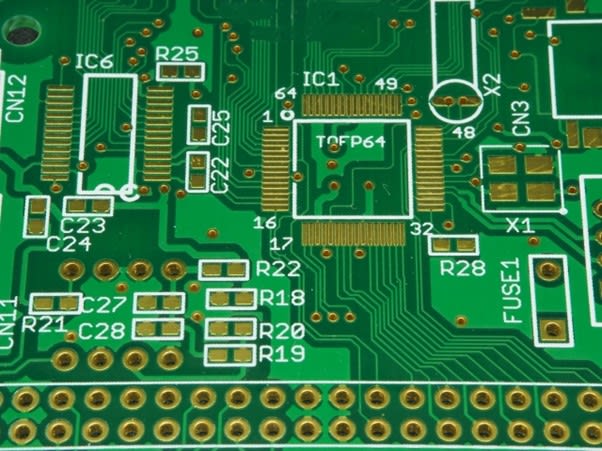
VCOの仕様を決定するには、一般的に「公称周波数範囲」を明確化することから始められます。つまり、VCOを組み込むことによって得られる最小・最大周波数を求めることが第一歩です。
それ以外にも、公称周波数や中心周波数を同調範囲として指定して計算することもできます。
また、VCOが制御ループ内にあるアプリケーションについては、同調感度はVCO素子の出力ともなり、ダイナミクスと安定性に影響を与える可能性が考えられます。
VCOの出力電力については、インピーダンスの負荷に供給される電力を指定します。一例を挙げると、RFVCOの場合において、一般的に50オームです。
また、バッファアンプを構成に組み込むことによって、負荷の絶縁性を高めることもできます。ほかにも、関連する用語について解説すると以下のようなものが挙げられます。
- 電源プッシュ:電圧の変動によってVCO出力周波数へ与える影響
- 位相ノイズ:VCOの信号純度を示す。位相ノイズは時間間隔誤差(TIE)として顕在化させる
VCOを使った新しい2つの技術
VCOを使った新しい技術は、以下の2つが挙げられます。
- モジュール方式
- モノリシックVCO
ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
1.モジュール方式
モジュール方式は、1970年代から開発が進められている技術です。VCOモジュールは、ディスクリート部品で構成された発振器の小型版だといえ、金属製ハウジングの基板上に構築されています。
モジュール方式のVCOは単独で完結する仕組みとなっているため、求められる要件に制限が少ないことが特徴です。求められる要件には以下のようなものが挙げられます。
- グランド接続:回路動作の基準となる電位
- 電源電圧:電子回路を動作させるのに必要となる電圧
- 同調電圧:位相同士が打ち消し合う電圧
- 出力負荷:回路が耐えられる最大出力負荷
また、旧来使用されてきたディスクリートVCOは、周波数をカスタマイズできることが特徴でした。しかし、部品ごとのばらつきを抑えるため、製造時に大きなコストやリソースを割いて調整することが求められます。
しかし、モジュール方式のVCOを採用することによって、これらのデメリットを解消しながら安定した発振性能を得られるようになりました。
2.モノリシックVCO
モノリシックVCOは、VCOの回路要素とされる以下のものが1つのチップに内蔵された技術だと定義されています。
- トランジスタ
- コンデンサ
- 抵抗器
- インダクタ
- バラクタダイオード
1つのチップ上に完全なVCOを構成でき、求められる要件はモジュール方式に加えて、制御ラインへの接続のみとなっています。
初期のモノリシックVCOは、通信に必要な帯域に対応できなかったため、市場へ影響を与えることはありませんでした。しかし、コンデンサやシリコンIC技術の発展とともに800〜2500MHhzの帯域に対応できるようになり、あらゆる機器に搭載され実用化されるようになりました。
モノリシックVCOの技術は、あらゆる製品に活用されており、TVチューナーやGPS、Bluetooth向けのワイヤレス集積回路に組み込まれています。そのため、今後も無線機器を始めとした製品へ搭載されることが予測できます。そのため、引き続き高い需要がある部品だといえるでしょう。
VCO(電圧制御型発振器)についてよくある5つの質問
VCOについてよくある質問には、以下の5つが挙げられます。
- 質問1.VCOとはどういう意味ですか?
- 質問2.VCOが発振する原理を教えてください
- 質問3.周波数を変える仕組みにはどのようなものがありますか?
- 質問4.可変周波数発振回路とはなんですか?
- 質問5.VCOは具体的にどのようなものに使われていますか?
ここではそれぞれの質問に対する回答についてご紹介しますので、詳しく見ていきましょう。
質問1.VCOとはどういう意味ですか?
VCOとは、電圧制御発振器のことを表す用語です。出力周波数と入力電圧が比例する電子回路となり、基本的には周期的なAC信号を生成します。
しかし、VCOを使用することによって、発振周波数を入力する電圧によって制御することが可能です。この性質から一般的な家電から通信機器まで幅広い領域の精密機器に使われています。
質問2.VCOが発振する原理を教えてください
VCOは、発振回路を構成するコンデンサにバリキャップダイオードを取り入れることによって共振周波数を変化させます。
この仕組みによって発振周波数を制御し、バリキャップダイオードに加える電圧をコントロールすることで発振周波数に高低をつけることが可能です。
さらに、変調したい信号をバリキャップダイオードに与えることによって、周波数を制御して出力することもできます。この際、変調する信号に可能な限り影響を与えないように小さな容量のコンデンサを採用することが一般的です。
また、外部からの影響を最小限に抑えるために、緩衝増幅器を回路に組み込む場合もあります。
質問3.周波数を変える仕組みにはどのようなものがありますか?
電圧や周波数を適宜、最適化するには、交流を直流に変換したあと、再び交流に戻す工程が必要です。この工程を実現する装置を「インバータ装置」と呼びます。
交流から直流にする回路をコンバータ回路、直流から交流に変換する回路がインバータ回路です。これらの装置を総称してインバータと呼び、電圧や周波数を自由に制御する仕組みだといえます。
質問4.可変周波数発振回路とはなんですか?
可変周波数発振回路とは、発振する周波数を変更・制御できる回路です。こちらの回路には、あらゆる種類があり、その中でも電圧によって、発振周波数が制御できるものがVCOと呼称されています。
VCOは、位相同期回路などの用途に利用され、電子機器に電圧で可変する回路を追加することによって、活用されています。
質問5.VCOは具体的にどのようなものに使われていますか?
VCOが使われているものを具体的にご紹介すると、以下のようなものが挙げられます。
【家電製品】
- テレビ
- ラジオ
- ブルーレイレコーダー
【通信機器】
- 固定電話
- スマートフォン
- パソコン
一般的に、電力を用いて出力する周波数を制御する必要がある電子機器に幅広く使われています。上記の例からテレビのVCOの使われ方を解説すると、アンテナから入力された信号が選ばれ、増幅されます。さらに変換と復調を繰り返して最終的にアナログ信号としてテレビ画面へと出力される仕組みです。
この工程ごとに異なるVCOが使用されており、ノイズの除去や電圧や信号の増幅、周波数を安定させたうえで音声や映像を出力します。
つまり、入力から出力までに必要な周波数の調整を行い、最適化するために欠かせない装置だといえるでしょう。
まとめ
VCO(電圧制御型発振器)について解説しました。VCOは、入力された電圧によって、異なる周波数を出力する性質があり、電子機器を正常に動作する役割が求められます。
この性質から家電や通信機器など、身の回りのあらゆる製品に組み込まれており、私たちの生活になくてはならないものとして、今もなお進化し続けています。
VCOの役割や仕組みについて理解を深めたい方は、ぜひこの記事でご紹介した内容を参考にしてみてください。


