タイムドメインで考えよう

ノイズは周波数軸上でのスタティックな状況把握と対策が基本です。 いっぽう、ノイズが飛び交う空間はダイナミックに変動しています。
ノイズ対策は周波数領域が基本

図1:周波数領域でのノイズ規制(VCCIの例)
電子機器などから発生するノイズには、特定の周波数成分だけを持つもの、基本波と整数倍の高調波で構成されているもの、広い周波数範囲にわたって幅広い成分を有するもの、およびこれらが複合して含まれるものなどがあり、様々です。
こうしたことから、ノイズのエミッション(発生量)やイミュニティ(耐性)は、これまでスペクトラムとして測定され、周波数領域で評価・対策されてきました。ノイズの規制なども概ねこの考えに沿って策定されていることもあり、現状では「ノイズのスペクトラムを規格のリミット以内に納めること」がノイズ対策になっている一面があります。
図1は日本のVCCIで規定されたエミッションの規制値です。機器から発生するノイズのスペクトラムピークがこの規制ラインを超えないことが設計上の最低目標です。例えば、機器内部のクロック信号は鋭い立ち上がりを持ち、レベルも大きいうえボード上で長く引き廻されるため大きなノイズ源になりがちです。さらに、安定した周期信号であることから、基本波と高調波のスペクトラムは細く先鋭的になりノイズの規制値を超えてしまうことがあります。

図2:SSCの例(データはMAXIM)
この問題を回避する手段としてよく用いられる方法のひとつに「周波数拡散クロック(Spread Spectrum Frequency Synthesizer Clock:SSC)」があります。周波数拡散という名がついていますが、無線通信で使われるような拡散符号を使った大掛かりなものではなく、クロックをキャリア(無線搬送波)として三角波でFM変調するものがほとんどです。クロック周波数をわずかに変動させることで、各々の周波数成分(スペクトラム)が広がりを持つようになります。トータルのパワーは変わりませんから、ピーク値は減少し規制をクリアできるという訳です。
図2は実際のSSC用ICの特性例です。ピークが20dB以上減衰する結果が得られています。拡散の量を増やす、つまりクロックタイミングの揺らぎを大きくし過ぎるとシステムの動作が不安定になることや、ジッタによるエラーの要因となる、またクロックをデバイスの上限周波数付近で使っている場合は周波数を下げる方向に拡散するといった注意点はありますが、改善される量が大きいことから、最近では初めからSSC機能を内蔵しているICも多くなりました。
変動するノイズ
個々のノイズが持つ周波数成分の傾向はそれぞれ異なるので、スペクトラム(つまり周波数領域)で測定したり対策したりするのはノイズに対する最も基本的なアプローチです。SSCも周波数領域で考えられたノイズ対策の典型と言えるでしょう。
ですが、「ノイズは時間と共に変動する」という性質も持ち合わせています。機器の設定や動作状態によってノイズの出方も量も変わるほか、携帯電話などのように移動するアイテムでは、場所や持ち方などでノイズのエミッションもイミュニティも変動します。さらに、デジタル機器ではごく短い時間の中でノイズの量が大きく変わるものが多数あります。実際に電波やノイズが飛び交う空間は静的ではなくダイナミックに変動しているわけです。
こうした変動するノイズに対して、従来からの周波数領域からのアプローチは十分とは言えません。ノイズは定常的に一定量が出るものとして測定法や規格が定められてきたからです。短時間に起こる変動を考慮してピークホールド、準尖頭値(Q-peak)、平均値などの検波方式が規定されており、それらを切り替えることで比較することはできますが、評価という要求に対しては不十分です。さらに、ノイズの影響を受ける機器や回路はノイズのスペクトラムに応答するという保証はどこにもありません。
また、ノイズを出す側でのデジタル化が進展する一方で、ノイズの影響を被る機器もデジタルである場合が多くなっています。そうした場合の対ノイズ性能は、ノイズのスペクトラムよりも機器やシステムの基本特性としてのBER(bit error rate)などで評価するのが一般的です。
注目されるAPD

図3:しきい値を超える時間確率
こうした背景から、ノイズを時系列的に変動するものとしてとらえ、タイムドメイン(時間領域)で評価・測定する方法が各方面で研究され、具体的な応用が進展しています。図3に示したように、スペクトラムをリアルタイムで観測できるスペクトラムアナライザの出現によって、ノイズや電波の干渉などを周波数領域と時間領域の双方からとらえることができるようになったことも成果の一つですが、最近注目されている評価法としてAPD(Amplitude Probability Distribution:振幅確率分布)が挙げられます。APDは、「妨害振幅が一定レベルを超える時間確率の累積分布」と定義されています。
具体的にはまず、周波数を固定したスペクトラムアナライザやノイズ受信機から信号レベル出力(包絡線検波出力)を取り出します。そして出力をコンパレータとカウンターなどを組み合わせた時間累積回路を使い図3の様に特定のレベルを超える時間を積算し、全測定時間に対する割合(時間確率)を求めます。
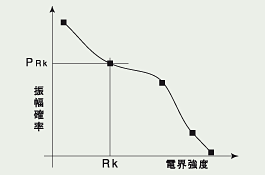
図4:APDプロット
同時に、時間確率がほぼゼロから1になるまで順次コンパレートレベル(電界強度の検出値)を変えた時間累積回路を並列に接続して各々の電界強度に対する確率をプロットしAPDの曲線を得ます(図4)。この場合、例えばAPD1(%)値とは、その値を超えるノイズが到来した時間の合計が全観測時間の1%になるノイズの大きさを意味します。

図5:電子レンジのAPD
(グラフはCISPRの資料を元に本誌で作成
APDを測定すれば、どのくらいの大きさのノイズがどのくらいの時間的割合で発生しているかをビジュアルに捉えることができる訳です。ちなみに図5は市販の電子レンジ6台についてAPDを実際に測定した結果を表したものです。機種によってカーブに違いが見られますが、こうした違いを周波数領域で表現することは困難であり、APDの有用性を納得できます。
CISPRでもAPDを採用
APDは、動作状態や設定などによってノイズの状態が時間的に変動する機器に対して有効な評価手段であることがわかってきました。このことを受け、ノイズを規制する規格などでもAPDの考え方が導入され始めています。
例えば、CISPR(国際無線障害特別委員会)では既に採用が始まっています。具体的にはCISPR 16-1-1 2003(無線妨害及びイミュニティ測定機器及び方法の仕様-PART1-1:無線妨害およびイミュニティ測定機器-測定機器)でAPD測定機能が項目として追加(修正)されています。 この修正(Amendment 1)では、「APD測定による測定結果は、妨害がデジタル通信システムへの妨害を引き起こす潜在性と良い相関性を有すること」および「APD測定が電子レンジなどの製品又は製品群へ適用されることを意図して制定されたこと」を謳っています。さらに、妨害波がデジタル通信システムへの妨害を引き起こす潜在性を決定したいときにAPD測定を適用することを勧めています。
ちなみにAPDの採用は日本からの提案に基づいており(※1)、APDの研究は日本が一歩抜き出ているとも言えます。
※1:野田臣光 吉田和浩「マグネトロン応用機器におけるEMC設計上事例」 EMC2006.8
APDの今後
ノイズは様々なスペクトルを持つことから、APDも測定する周波数や周波数帯域幅によって異なる値を持つと考えられます。
この場合、どの周波数で測定するのが相応しいのかはアイテムによって異なるはずです。それらはデータの蓄積によって経験的に定めていくことになります。場合によってはAPD曲線を周波数毎に描く3次元的な表現が求められることもありそうです。また、最終的なBERとの関係については相関性が実証されつつありますが、周波数と同様にノイズを出す側と受ける側のアイテムによって事情は異なるため、アイテムに依存しない一般化された相関の合意形成には今少し時間がかかりそうです。
いっぽう、APDの応用面では電子機器の内部で発生するノイズの評価などにも有効であることが分かってきました。電子機器内にはノイズを出す部品や回路と共にノイズの影響を受ける回路が同居しており、自らの機器内部で発生するノイズによる誤動作やS/Nの低下などのいわゆる「自家中毒」が問題になっています。これに対してAPDはBERのようなノイズを受ける側の回路動作を念頭に置いているため、状況の把握や対策に直接結びつきやすいメリットがあります。最近では微小なセンサの位置をスキャンして機器内のAPDの分布を求める(※2)といったことも行われています。
※2:風間智 蔦ヶ谷洋「無線機器のEMC対策に向けて電磁雑音の新たな評価手法を提案」日経エレクトロニクス2006 2-13